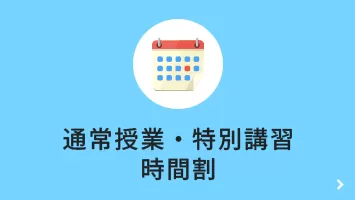「思考力」重視の落とし穴——いまこそ「知識の力」を見直すとき
最近の教育現場では、「知識より思考力が大事」とよく耳にします。
「考える力を育てましょう」「答えのない問いに挑もう」など、聞こえはとても良い。
しかし、私は塾の現場で日々中高生と接していて、少し違和感を覚えるのです。
「そもそも考えるための材料が足りていないのでは?」
これは、全国学力調査の結果からも読み取れます。
たとえば、「素数」の定義をご存じですか?
「1と自分自身以外では割り切れない数」です。
では、1から9の中で素数を選んでくださいと言われたとき、正しく答えられる中学生は、なんと全体の3割ほど。 正答率は32.2%。残りの7割近くの子どもたちは、間違えるか、答えないか、です。
正答率は32.2%。残りの7割近くの子どもたちは、間違えるか、答えないか、です。
同じく国語でも、漢字の意味を問う問題——「会心」「改心」「改新」の中から、「展示する作品はどれも〇〇の出来だ」という文脈に合うものを選ぶ問題——の正答率はわずか35.7%。
言葉の意味を知らないということは、文章を正しく読むことができないということ。
そして読み取れなければ、当然、考えることもできません。
実際、記述式の国語問題の正答率はどれも30%台。なかには27%が無回答という問題もあるのです。
「考えて答える」以前に、「何を聞かれているかが分からない」「どう書けばいいかが分からない」という状態なのでしょう。
知識を「詰め込む」ことの本当の意味
ここで、多くの保護者の方が疑問に思われるかもしれません。
「昔みたいな詰め込み教育に戻すってこと?」 たしかに、意味も分からず暗記だけをさせられるような教育では意味がありません。
しかし、「知識を持つこと」そのものは、決して悪いことではありません。 むしろ、思考力を育てるためには知識が必要不可欠なのです。
たとえるなら、「思考力」は料理の腕前、「知識」はその材料です。 いくら素晴らしいシェフでも、食材がなければ料理はできません。 同様に、どんなに頭の使い方がうまくても、もとになる情報(語彙、背景知識、文法、歴史的事実など)がなければ、思考は深まりません。
「地頭がよければ大丈夫」という幻想
最近よく聞く言葉に「うちの子は地頭がいいから大丈夫」というものがあります。
ですが、現場で見ていて思うのは、
偏差値50〜60の子でも、「杞憂」「一抹の不安」「初志貫徹」など、一般的な語彙を知らないケースは珍しくありません。
このまま知識の「土台」が抜けたまま中学・高校を終えた場合、大学に進学しても文章が読めない、書けない、調べても意味が分からない、という状態に陥りやすいのです。
なぜ「知識」を身につけるべきか
知識があるということは、「選択肢が増える」ということです。
・読める文章が増える
・書ける表現が広がる
・言葉で説明できる力がつく
・自分の考えを他人に伝えられる
そして何より、「分からないことに出会ったとき、どう調べればいいかの勘が働く」ようになります。
これはまさに「学ぶ力」の土台です。
まずは家庭でできることから
思考力を育てるのは大切です。ただし、いきなり“深い問い”を投げかける前に、まずは日々の知識の積み重ねを大事にしてあげてください。
家庭でできることは、意外とシンプルです。
-
漢字や語彙を一緒に学ぶ
-
難しい言葉が出てきたら調べて一緒に話す
-
「なぜそう思うの?」と聞き返してあげる
-
文章を書く機会(手紙・作文・感想文)を日常に入れる
こういった“地味な積み重ね”こそが、知識とともに思考力を育てる一番の近道だと私は考えています。
地に足のついた学びを取り戻そう
「思考力重視」という旗印は美しいかもしれませんが、教育の本質は、地に足のついた知識の積み重ねの上にこそ成立します。
すぐに花開かなくてもいい。知識という“根っこ”を、しっかり育てていきましょう。
そして、子どもたちが本当に自分の頭で「考えられる人」になれるよう、私たち大人も「考える材料」を与えられる存在でありたいですね。